九月号の歌
(選者・編集人)
さいたま 古 賀 多三郎
ふるへをののく足を踏みしめゆかむにもゆるやかなこの坂ただ長し
狭 山 大河原 惇 行
ここにありてさらに何かに及ぶ思ひ光の動くわが指の先
東 京 間 瀬 敬
夏の雲高く崩れてわが頭上千代田区過ぎて港区に入る
熊 本 松 本 東 亜
ムクの葉を椀の磨きに使ふこと知りて手に取る今日の歩みに
兵 庫 藤 田 信 宏
海はひと色煙はひと刷き意志もちて要点のみを描きあるなり
我孫子 杉 本 明 子
ふたりある日々また日々の過ぎゆきに花茎ながく蘭は咲きたり
所 沢 伊 藤 光富久
寄りてきて離れゆきたる鳩一つ幼の手には豆はそのまま
東 京 井 出 匠
寅さんがバスを待ちたる山の道バス停のみが残されてあり
東 京 小 川 優 子
庄内の流れに沿ひて鈍び色の瓦いく千連ねて何処まで
(若い会員)
日 立 桜 井 敏 幸
キャンバスに塗りて初めて明るさが少し違ふと吾は目を止む
須 崎 小 松 桂 子
曇天に青き光を引きながらルリタテハ一つ飛びてゆきたり
高 知 井 上 佳 香
おもむろに体を起こし草むらへ入りゆく蟇の足の大きさ
狭 山 大 島 元 子
あたらしき生活求めてパソコンを使ひて地図を幾度か見つ
岡 山 木 戸 京 子
幼子の淡き記憶に入道雲は尾鈴の山に真つ白くありき
正岡子規短歌合評(二十一) 明治三十三年
いたつきの病の牀をおとづれし年ほぎ人に酒しひにけり
【藤田信宏】詞書に「麓左千夫など来りたるに」とある歌である。病に苦しむ床を新年の言祝ぎのために訪れた岡麓や伊藤左千夫などに酒を強いた、というのである。「いたつきの病の牀をおとづれし」には、病床を訪れた友らへの思いが籠っている。「いたつき」は、骨折り、苦労、病気といった意味であるが、「いたつきの病の牀」と言うことにより、生きた調べになると共に切実さが強く漂っている。下句「年ほぎ人に酒しひにけり」は、状況を実に素直に表現しており、何気ない言い方の中に深い情感が表れている。この歌も現実感が濃厚で、読む者の心を揺さぶる。この年一月に執筆した随筆「新年雜記」に次のような一節がある。「復新年を迎へた。うれしいうれしい。其『うれしい』がまだ盡きぬ内にはや次の大問題は首を挙げて來る、『来年の正月は』。さて此大問題に逢著したところで『なに今年も』とやつてのける勇気は最早なくなつた。……とにかく来年の正月迄は生きる積りだ。といつては見たが『とにかく』『迄は』『積りだ』といふ言葉を省く事が出來なかつた。」(アルス版『子規全集』第十巻)。子規の心中では、来年の正月まで生きる自信が揺らいでいたのである。そうした精神状態の中での麓や左千夫等の訪問なのであり、これが嬉しかったであろうことは想像に難くない。「酒しひにけり」には、友らへの人間的な深い情愛と共に、切実な生の哀感が表れている。
【小川弘】前評者の解説により、理解が深まる。「いたつきの」は「病」にかかる枕詞的に使われているようで、そのまま読み下して構わないと思う。新年の祝いの言葉を述べに来た岡麓(明治十年―昭和二十六年)と伊藤佐千夫に酒を出してもてなしたことを詠っている。岡も伊藤も子規の弟子としての礼を取っているので、子規も嬉しかったのだろう。岡麓の家は徳川幕府の御殿医であり、子規に入門した当時は豊かな生活をしていたらしい。昭和に入って生活のために女学校で書を教えたという。子規は周りに人がいることが好きで、痛いと呻きながらも来客の応接を家族にやらせたという。「酒しひにけり」に子規の交際好きな性格が表れているように思う。
【保泉栄子】この一首では「年ほぎ人に酒しひにけり」に眼目がおかれているので「いたつきの」は、小川評のように枕詞的に使われたと思う。「久方のアメリカ人のはじめにしベースボールは見れど飽かぬかも」(明治三十一年)の「久方の」もアメ(雨)にかかる枕詞として使われているので、さりげなく使ったものと思われる。麓らが病む自分のもとに新年の挨拶に来てくれたことが嬉しくて酒を強いているのである。内心は翌年の正月まで生きられるか煩悶していたことを思うと「酒しひにけり」の客観的ないい方が、いっそう胸に迫る。
【松本東亜】新年の祝酒を勧める子規の温か味を感じる一首である。結句は「無理して飲んでもらったことよ」というような思いであろうか。子規は飲めない体であるが、岡麓や左千夫は飲んで話も弾んだことだろう。子規は嬉しかったに違いない。
【間瀬敬】明治三十三年一月三日、伊藤左千夫は桐の舎桂子の月次歌会で知り合っていた岡麓と落ち合って、初めて子規を訪問した。その時の子規の歌で、「酒しひにけり」は「屠蘇」ともあるので、そうなのだろう。事実そのままを詠んだものであるが、「酒しひにけり」にその折の情景がよく出ている。
【古賀多三郎】この時子規と左千夫は初対面だったらしい。左千夫の開眼の日だったといっても過言ではないと思う。この時子規、左千夫はいかなる歌論を展開したのか。この後の左千夫の変貌ぶりを思えば、想像にあまりあるといえよう。
【大河原惇行】先の一首と比べて、表現として、この一首にあっても、子規は、少しもぶれていない。そのままを、文字として示し、そのままを、ここに提示しているだけなのではないか。その思いが、生きての思いと重なるそのさまを、ようやく、自らのものと為し得るようになったのであろう。そして、「いたつきの病の牀をおとづれし」は、短歌にあって、序にあたるところなのである。一首にあって、この導入が、如何にも自然であるので、「年ほぎ人に」の反応が、生きていると受け止めていいのではないか。思いが流れるように、文字となっていると見るのだ。このように、子規が表現者として、力を得たときに、左千夫に逢い得たことに、ぼくは、単なる偶然を越えた、何か時代の力のようなものを、受け止めているのであるが、如何なのであろう。左千夫は、子規に直接会って、変わるのである。子規という人間にふれて、左千夫自身が動いたということになるのであろう。そこに、一つの時代の機微を受け止めるのであるが、これは、ぼく自身の勝手な思いといっていいのかも知れない。もしも、左千夫が、もう少し、早く子規に逢って、その人間にふれていたら、表現者として、別の子規に触れていたのであろう。そのようなことにも、思いが及ぶのである。偶然が偶然を越えて、時代に生きることも、一人の思いとして、楽しいことであると思うのである。
上野山夕こえ来れば森暗みけだもの吠ゆるけだものの園
【杉本明子】明治三十三年「森」七首中の冒頭の一首。子規三十三歳の作。けだものの園は明治十五年に日本で最初に開園した東京都恩賜上野動物園のことと思う。斎藤茂吉も 「上野なる動物園にかささぎは肉食ひゐたりくれなゐの肉を」と詠っている。「けだもの吠ゆるけだものの園」とかさねた表現に注目した。夕方となり森はいっそう暗く、そこに獣の声が響き渡っていると具体的な動物の名を出さず大きく捉えている。また「動物」ではなく「けだもの」と表現されていることに微妙なる語感の差を感じる。
【熱田君江】子規の時代の上野の森の夕べは、今より随分暗かったと思われる。そこにある動物園に飼われていた諸々の生き物の鳴き声は、夕べになると一層鮮明に聞こえて来たと思われる。その中でも大自然を走り回っていたであろうライオンやトラのような、所謂「けだもの」の声は怖い、というより、子規にとっては哀切極まりなく聞こえたのではないのだろうか。「けだもの」という言葉を繰り返し使ったのもそういうところに心が動いたのではなかろうか。
【向山文本】明治三十三年の子規の病状が悪化する前の作品と思うが、外出した帰りの上野山の夕の情景をそのまま詠ったものと思う。前二評者と同じく「けだもの吠えるけだものの園」の表現には注目してしまう。日本ではじめての動物園の情景をこのようにとらえていることの意味も詮索してみたが、やはりこの歌はこの表現をそのまま受け止めればよいのだろうと思った。情景も表現も強く印象に残る作品である。
【松本東亜】動物園を歌の材料にして詠んだことが新しい試みではないだろうか。しかし、動物園とは句に入れてない。「けだもの吠ゆるけだものの園」と工夫している。深閑とした中に聞える動物の声は、少々恐ろしい雰囲気が感じられる。
【間瀬敬】今上野の山を歩いても、動物の声が聞こえてくることはほとんどない。騒音対策などにもよるだろうし、周りの喧騒にもよるのだろう。今でも夜に虎やライオンなどの声が聞こえたら、それはそれなりに異様だろう。時代の差というものを感じる。「けだもの吠ゆるけだものの園」が直接だ。「けだもの」の語については、実朝に「物いはぬ??(??)の?(????)すらだにもあはれなるかな親の子を思ふ」があった。また、「上野山夕こえ来れば」も実朝の「箱根路をわが越えくれば」がある。そういうものの影響のもとに作られているのだろう。【古賀多三郎】子規、茂吉のみならず、上野動物園は、多くの文人墨客がこころを寄せている。これは外国のめずらしい動物への興味ではなく、これら動物の生態のかなしさへの思いであろう。狭い檻の中で夢遊病者のように歩きまわっている虎やライオンの様子は痛んだ文人らのこころを慰め、またそのかなしい生態に一層こころを痛めたに違いない。それは明治の文人が西洋から得た自我の意識の痛みであったのであろう。子規のこの歌にもそのかなしさ、痛みが、にじんでいるようである。
【大河原惇行】この一首も、流れるように、文字となっているとみていいのではないか。歌い出しは、序にあたるところであるが、「上野山夕こえ来れば」の表現は、実際をそのままの文字となっているのではないか。子規が、序をこのような表現として、自らのものとするまで、どれだけの努力を重ねたことか。そのことに、考えは及ぶ。そして、反応として、さらに表現として、優れているのは、「森暗み」と、実体について、反応をして、その実体を文字にしているところなのではないか。そう思うのである。このような何でもない、表現ができるので、下句にかぶさるその序の部分が、他の人の及ぶところでない世界のものとなっているのであろうか。この表現があって、「けだもの吠ゆるけだものの園」が、全く新しい世界のものとして、ここに提示されているのが、この一首ということになるのであろう。
日々点描・119
「往還集の表現・十八」抄 大河原惇行
湯元の道75
春の日の過ぐらく知らに草臥れし子は道の上を這ひてたはむる
ここまで、書いてきて、いろいろと手をやいているのである。その意味するものは、一体何なのか。とにかく、これらの作品の背景に、何かわからない、何かが動こうとしているのではないか。大きな意味でいえば、この後の文明の作品の展開にあって、凡そのことは頭に入っていて、理解しているのであるが、それでも、一首一首の作品に、向き合って、自ら一人の思いとして、文明の作品に直接ふれてみると、さらに、簡単でないことが分ったということになるのだ。
端的にいって、この一首は、「草臥れし子は道の上を這ひてたはむる」と、いうのが、その意味するところではないか。
「子は道の上を這ひてたはむる」に、どれだけの意味があるというのであろう。今までの物差しでは、測ることができない何か、そこに、把握の意味を求めているのであろう。
これから、じっくりと向かわなければならない。
16・1・7・10
或る友を思ふ76
ただひとり吾より貧しき友なりき金のことにて交絶てり
単純な一首である。ただ、「金のことにて交り絶てり」と、「ただひとり吾より貧しき友」を、そのまま文字にしているだけなのだ。土屋文明は、東京帝国大学を卒業しているといっていい。そのような時代を通しての一人の友のことを、ここに、このような形で、提示をしているのではないか。
人間の生きる本質を、このように言葉して、示すその背景として時代をみるのであるが、まさに、そこに、表現というものを求めたということになるのであろう。
これが、社会とその経済に一人の身をおく、時代なのである。つまり、「金のことにて」に、要約されたその時代がそのまま文字となっていると読む。
文明の歌の一歩が、このように足を運び、足を置くところ、時代そのものに、これからの世界の啓示を示す、ものとなっているのであろう。時代の新があり、時代を超えた真が、ここにあるということではないか。 16・1・8・1
現代の一首
終戦の日の思はれて消ゆるなし一本の木のまぼろしに立つ
横山岩男
『春遊』につづく第八歌集『青桐』より。平成二十三年から同二十八年までの作品三六七首を収める。
この終戦は一九四五年の第二次世界大戦の終結のことであろう。したがって一九三三年生まれの作者は当時十二歳であったと思う。少年であった作者は「個を越えし未来いかにと炎天に佇み思」ったとその時の心理を歌にいう。
掲出歌の前には「終戦を聞きしは同級生の友にして炎暑の昼の巴旦杏の下」があるのでまぼろしの木は巴旦杏かもしれないが、終戦の日と関連して一本の木が作者の心に消えることなく立ち続けているということに心ひかれる。その一本の木は自身の精神そのものであり、終戦からの長い年月七十余年を経てもなお消えることなく心の裡に立ち続けるということに作者の生きてきた姿勢が窺える。矜持であり拠り所でもあったことだろう。
「まぼろし」は使い方の難しい言葉であるがこの一首にあっては、気分に流れることなく活きている。また三句切れの詠法もその思いを表現するのに効果をあげている。
(杉本明子)
暮れなづむ光残れる鯉の丘向ひて独り来し方偲びつ
能見謙太郎
『鯉丘残照』は能見謙太郎の第十六歌集。私事ながら、作者とはいわば同郷であり、私が短歌を始めた頃からお世話になっている。あとがきに「清少納言が『枕草子』にまで取り上げている「吉備の中山」が我が家の前の田園を挟んで(略)長く横たわっています。(略)なだらかな丘が三つ連なっていて、(略)頼山陽が鯉の泳ぐかたちに見立てて「鯉山」と呼称し、爾後地元ではこの呼び名が広まっています。(略)私が勝手に「鯉丘」ともじって見たまでのことで他意はありません。」とある。「吉備の中山」か「鯉山」か、我々には楽しい論争である。ちなみに、作者も両方を詠んでおり、「青田のなか吉備の中山横たはり吉備津の宮の千木光りをり」「朝朝に過ぐる鯉山の道すがら小暗きなかに元義の石」などの歌がある。掲出の歌は、大きな円熟を得た人の達成感、追憶、生への愛おしみなどの思いがしみじみと詠み込まれている。
この歌集には旅行、家族(特に妻の死)、友人などが詠まれているが、とりわけ作者の自宅近くの吉備津神社や細谷川が繰り返し、繰り返し詠まれていて味わい深い。作者の足跡を追ってみたくなった。
(木戸京子)
|

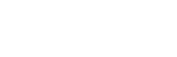
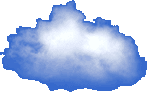

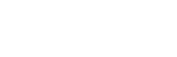
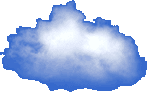
![]()